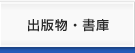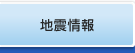書庫 > コラム
スコピエでの経験−私の国際交流(その4)
東京電機大学 教授 片山 恒雄
スコピエ暮らし
スコピエはマケドニア共和国の首都である。私は、スコピエに二度行ったことがある。一度目は1977年の冬から春にかけての3ヶ月半ほどで、家内と長女と一緒だった。次女はまだ生まれていなかった。二度目は、1982年11月から12月にかけての6週間ほどで一人だった。最初のときは、私が2週間位先に行っておき、家内が当時5歳の長女を連れてくるのを、ベオグラードまで出迎えに行った。なんとなく陰鬱な天候から、長女は先を予感したのかもしれない。着いた日から日本に帰りたいとぐずっていた。到着の翌日、ベオグラードの動物園に連れて行ったが、ほとんどお客もおらず、ライオンがいるはずの檻に、長靴が1つころがっていた光景を今でも思い出す。
当時、マケドニアはユーゴスラビアの一部で、スコピエは人口50万人の都市であった。ユーゴスラビアの東南部にあってギリシャと接しているマケドニアは、天然資源も乏しく、ユーゴスラビアの中でも最も貧乏な地方である。その上、50万都市なのに中華料理屋の一軒もなかった。グランドホテルという名前だけは立派だが、なんとなく貧相なホテルしかなかった。
1963年に、スコピエ地震があり、その後、ユネスコの肝いりで、スコピエに地震学と地震工学の研究所がつくられた。大学院レベルの教育と研究を行っていて、それまでにも日本からも何人かの先生方が教育に協力しておられた。その一人が久保慶三郎先生で、私を推薦してくださったのである。久保先生は研究所界隈では大変な人気者だった。まだ、研究所が市内にあったときだったから、夕方になると、毎日のように、レストランでワインを空けていたらしい。帰国のときには、レストランの楽隊が空港まで来て、お別れの曲を演奏したそうだ。
3人暮しの一度目
私は37歳だった。オーストラリアでティーチングフェローをやったことはあったが、外国で本格的に教えるのは初めての経験、それに5歳の娘を連れての3人の外国暮らしということで緊張した毎日だった。街に出ると、珍しい動物にでも出会ったかのように注目される。研究所の一歩外では、英語はまったく通じない。銀行などで待たされても、いつまでもじっと待っているしかないのだ。お米が買えるので、ご飯に困ることはなかったが、米から小さな砂利を取り除くのが日課だった。長女はこの事だけはよく覚えている。
スコピエ地震で被害を受けた市中心部の復興計画には丹下健三の案が採択され、10階建て程度のモダンなビルがつくられていた。私たちは、そんなビルの1つの8階にアパートをもらった。決して広いとはいえなかったが、3人家族には十分な広さで、中のデザインもなかなか洒落ていた。滞在中の1977年3月4日、マグニチュード7.2のルーマニア地震が起こって、スコピエも大きく揺れた。私たちのアパートも、確かに大きく揺れはしたが、外に飛び出すほどのものとは思わなかった。私たちの家族を除いて街中のひとが通りに逃げ出したように思えた。土木学会がこの地震の調査団を派遣(団長:久保慶三郎)、調査の後、その1員の伯野元彦先生さんがスコピエに来られて2ヶ月半ほどスコピエでご一緒した。あれ以来、家内は伯野先生の大ファンである。
今でこそ、研究所は、町はずれに立派な建物を持っているが、その頃は街なかの古びた建物の中にあって、もう一度地震が来たら、真っ先に倒れてしまいそうだった。
講義は1週間に2回だったが、私が英語でつくる講義ノートを秘書がマケドニア語に訳すというプロセスが大変だった。ノートづくりに授業の何倍もの時間がかかった。講義そのものも私が英語で話して、一区切りつくと、秘書がマケドニア語に訳すのである。教える相手は4人、そのうちの1人がゾラン(Zoran Milutinavic)だったが、今ではヨーロッパを代表する地震工学者の一人である。
全体にはそれほどレベルの高い研究所ではなかった。私だって30代半ば、こんな評価ができるほど、自分自身のレベルが高かったとは思えない。当時はまだ40歳代前半のヤキム・ペトロフスキがワンマン所長だった。国内には、そんなに仕事がない。所員を食べさせていくためには、研究所としての仕事を海外に求めなければならない。地震工学研究のプロモーターとしての海外での活躍を通して、ヤキムは国際的に知られた研究者になった。
家族と一緒だったおかげで、多くの研究者と家族ぐるみで親しくなった。こういう個人のつき合いがあとあと大いに役に立った。
1992年、スペインのマドリッドで世界地震工学会議が開かれたときのことだ。チトー大統領が死んで、ユーゴスラビアはいくつかの小さな国に分かれた。マケドニアもその一つである。これらの独立した国が別々に国際地震工学会の会員になることを申請してきた。私は、その四年前からこの国際学会の事務局長になっていたが、マケドニアという名前は歴史的にギリシャの一部だと、ギリシャの代表が猛烈に抗議してきた。ヤキムも負けてはいない。顔をくっつきそうに近づけてきて、私に文句をいってくる。あのとき、強面のヤキムに、「落ち着け、悪いようにはしないから」といえたのは、スコピエでのつき合いがあったからだ。結局、ギリシャの代表を口説き落として、マケドニアを入会させることができたし、そのときやり合ったギリシャの代表とも良い友人になった。ヤキムは数年前に亡くなった。ワイン好き、煙草を口から離すことがなく、しかも働き続けの一生だった。
国が崩れるのを見た二度目
オリンピック・ビレッジは、スコピエ郊外の山の麓の高みにある。チェスのオリンピックが開かれたときの選手村で、高級なモーテルのような居室からなる。一回目にスコピエに行ったときは、アメリカ人が何家族かいた。街なかにはアメリカ文化センターがあって、中国系のアメリカ人がセンター長を務めていた。鉱山エンジニアたちもいて、その多くはオリンピック・ビレッジに住んでいた。アメリカ人家族に一度招かれたことがあり、大きくはないが、長期滞在に適したなかなか良い雰囲気だった。私は、今度スコピエに来ることがあれば、是非ここに泊まりたいと思った。二度目にスコピエを訪問したときには、研究所もホテルのそばに新しい建物を建てて引っ越していた。思い通りにオリンピック・ビレッジに宿が取れたときは、前のときのアメリカ人家族みたいに、格好良く暮らせるものと思っていた。
ところが、現実は寂しかった。前に来たときに感じた、「今は貧乏だが将来は明るい」という雰囲気がまったく失われていた。国が崩れてゆく。チトー大統領が死んで求心力を失ったユーゴスラビアは混乱に入りかけていた。ホテルの食堂は2百人以上にサービスできる大きさだが、朝食を食べるお客が私だけということも少なくなかった。5,6人のウェイターが食堂の片隅で雑談している始末である。
2回にわたるスコピエでの経験もまた、アメリカの研究者と知り合うことだけが国際交流ではないと、私に再認識させたのである。(その4の終わり)
Copyright (C) 2001-2012 Japan Association for Earthquake Engineering. All Rights Reserved.