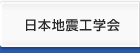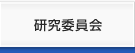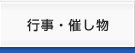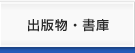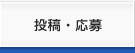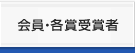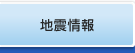会員 > 名誉会員
小堀鐸二先生のご逝去を悼む
京都大学防災研究所 鈴木祥之
 本会名誉会員 小堀鐸二先生は、2007年9月5日逝去されました。享年86歳でした。ここに先生のご冥福をお祈りするとともに、謹んでご報告申し上げます。
本会名誉会員 小堀鐸二先生は、2007年9月5日逝去されました。享年86歳でした。ここに先生のご冥福をお祈りするとともに、謹んでご報告申し上げます。
小堀鐸二先生は、1920年11月15日東京都にお生まれになり、1945年9月早稲田大学理工学部建築学科を卒業されました。1951年9月同大学大学院特別研究生前期を修了後、同年10月京都大学工学部講師に任用され、1954年3月同大学工学部助教授、1961年4月同大学防災研究所助教授、1962年4月同大学防災研究所教授に昇任され、地盤震害部門を担当、その後、1966年4月工学部教授に配置換、建築学第二学科建築基礎工学講座を担当されました。1984年4月停年により退官され、京都大学名誉教授の称号を授与されました。
この間、1979年4月から2年間、京都大学評議員として大学の運営、発展に貢献されました。1981年1月より4年間、日本学術会議会員(第12期)、1983年1月より2年間、日本建築学会会長などを歴任され、耐震工学、地震工学の先進的な研究を推進されるとともに指導的役割を担われ、多数の優れた人材を育成され、建築界に輩出されてこられました。
退官後は、1984年4月より1年間、近畿大学教授を勤められた後、1985年4月鹿島建設(株)代表取締役副社長に就任され、1986年11月に株式会社小堀鐸二研究所を設立、代表取締役として耐震・地震工学の実際への応用に尽力されました。1988年8月より1996年まで国際地震工学会理事、また1994年に設立された国際構造制御学会の副会長、1996年には会長を歴任されるなど国内外の学会の発展に寄与されました。また、1972年4月より2年間、文部省学術審議会専門委員、1970年12月より約15年間、建設省建築技術審査会高層部会長や1973年2月より12年間、通産省原子力発電技術顧問会会長など政府関係の諸委員としても尽力されました。
先生は、耐震工学、地震工学などの広い分野にわたって、数多くの先駆的な研究を推進され、耐震工学、地震工学分野の指導的役割を果たされ、優れた研究成果と多彩な研究活動は、広く学術および技術の進歩に寄与されました。なかでも動力学的な観点から研究主題とされてきた建築基礎地盤の動特性ならびに建築構造物の耐震性の研究における貢献は特筆され、非線形振動論、弾性波動論、確率論を基礎とする構造物の耐震設計理論は国内外の学界から高く評価されました。特に制震構造においては、制震システムの基礎理論の提唱のみならず、アクティブ制震を世界で初めて建築物に適用され、制震構造の発展に大いに貢献されました。このように学術・技術の発展の他に、建築行政、都市防災など行政に関わる面においても新たな施策の展開に指導的役割を果たすなど多大の貢献をされてこられました。このような先生のご業績に対し、数多くの賞を授与されておられますが、なかでも、学術研究活動においては1959年に「建築構造の耐震工学的基礎研究」によって日本建築学会賞(論文)を、1976年には「耐震建築に関する一連の研究」によって第20回京都新聞文化賞を、1990年には「地震工学の発展に関する一連の功績」によって日本建築学会大賞を授与されました。また、我国の原子力施設の耐震性向上に対する貢献により1985年には科学技術庁長官賞を、さらに1993年には先駆的な一連の制震構造の研究と技術開発に関して第3回日本建築協会賞特別賞、1997年には京都府文化賞特別功労賞を授与されました。
先生のご研究やご業績をご紹介するには、余りにも多くのものがあり、枚挙に遑がございません。先生の研究に対するお考えやお人柄が偲ばれる一端についてご紹介させていただきます。
先生が京都大学に赴任された直後は、棚橋諒先生の命により木構造の講義を担当されました。木材は、強度や乾燥収縮の異方性があり、また湿度、含水率、材種などによって材料特性が異なり、自然の材料が複雑な性質を有することの難しさを痛感されたようです。地盤も同じように自然にできたものであり、地盤の材料特性の難しさに加えて振動特性が上部の建物に及ぼす影響も大きいことから、地盤振動の解明に意欲を持たれ、その後のGround Complianceなど地盤関連の研究に繋がっています。
先生が京都大学に赴任された1950-1960年頃は電卓程度の能力しかない解析手段でしたが、地震の非定常性、構造物の非線形性に注目された研究では、アナログコンピュータをいち早く開発され、時刻歴地震応答解析を成し遂げられ、スカイスクレーパーの実現に結びつけられています。1964年に高層建築技術指針が、京都大学、東京大学の研究グループなどが中心となって作成されていますが、細かい規定を作るのは、将来の発展にマイナスになるとの先生のご意見で、高層建物の基準ではなく基本的な考え方を示す指針にされました。ここにも先生の絶えず前向きに考えられる姿勢が伺われます。
1960年10月からUCLAのW. T. Thomson先生のところに客員研究員として滞在された時に、Ground Complianceの研究をされ、この先駆的な研究は、その後の地盤−基礎の動的相互作用、構造物−地盤連成系の地震応答、不整形地盤の振動特性に関する研究へと大きく発展させておられます。UCLA滞在中にThomson先生から米国に残るように強く勧められました。折しも、米国では人工衛星、ロケットなど宇宙工学が盛んになり、優秀な人材を必要としたようです。しかし、1923年の関東大震災を幼少期に経験された先生は、その頃から地震に対する強烈な印象をお持ちだったのでしょうか、地震被害をどうしたら防げるかといった大命題に一貫として挑んでこられ、建築や地球から離れることができないとのことで、1961年3月に帰国されました。その後、1964年新潟地震、1968年十勝沖地震と巨大地震が相次いで起こり、また1978年宮城県沖地震による建物被害などが契機となった建築基準法の改正では、地盤の動特性を考慮した小堀・南井案を提案されました。
近年の地震学の発展は目覚しく、地震動予測がなされるようになったが、地震動を建築物への地震入力として考えるといまだ不確定であり、このような地震動からフリーになり得る制震構造は優れた構造技術であるとのお考えから、1989年には世界で始めてアクティブ制震の11階建ての東京・京橋センタービル(旧京橋成和ビル)を実現されました。1957年に「制振構造に関する一つの試み」という論文を世に出されてから半世紀、制震システムの理論のみならず、制震構造の実用化の端緒を切り開かれ、これ以後、国内外において多くの制震ビルが建てられるようになったことは周知の通りです。また、先生自らが尽力されて1994年に設立された国際構造制御学会の副会長、会長として国内外の学会の発展に寄与され、制震構造に関する応用面での貢献は著しく、耐震工学、地震工学の発展に先生の果たされた役割は計り知れないほど大きいものがあります。
小堀先生は、地震学の発展に多大な寄与をされ、地震災害軽減のために地震学の応用を考えておられた金森博雄先生と、これからは地震学と工学との融合をより一層図ることが不可欠であるとの思いがあり、以下のシンポジウムにも繋がっています。
2000年11月7日にCUREeと京都大学の共催のもとに国際高等研究所で開催された小堀記念シンポジウムEarthquake Engineering in the Next Millennium ”Symposium in Honor of Takuji Kobori”で、Joseph Penzien先生、金森博雄先生、金井清先生をはじめ、世界的な研究者が結集したシンポジウムであった。朝早くから紅葉の美しい国際高等研究所に国内外の多くの方が集まり、主会場であるレクチャーホールでは夜遅くまで地震工学と地震科学、制震構造の現状と展望について講演と議論が続けられたことは大変印象深いものでした。このようなすばらしい会議が開催できたのも、絶えず前向きに取り組まれる小堀先生のすばらしさによるものでした。
このシンポジウムでは、Wilfred D. Iwan先生がChairmanを、私がSecretary Generalを務めましたが、2008年10月に中国北京市で開催される第14回世界地震工学会議において、再びIwan先生とともにConvenerを務め、先生のご遺徳を偲ぶ小堀鐸二先生メモリアルセッション“Significant Accomplishments and Future Directions in Earthquake Engineering - In Memory of Professor Takuji Kobori”を開催いたします。
ここに、謹んで先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
Copyright (C) 2001-2012 Japan Association for Earthquake Engineering. All Rights Reserved.