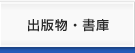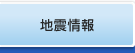書庫 > コラム
バンダアチェはいま(その3:最終回)
東京電機大学 教授 片山 恒雄
世界銀行の立場
3日目の午前中は、2日にわたったワークショップと私たちが現地を見た結果に基づいて、ジャカルタにいる世界銀行のインドネシア責任者と電話会議を行った。
世界銀行は、大口のドナーの1つである。自分たちがドナーであると同時に、MTF(多国籍基金)の実施を任されているという意味でも大口ドナーである。復興住宅の建設は、ドナーとしてやっているたくさんの仕事の1つであり、私たちはここに問題があると思った。よくあることだが、世界銀行としては、質よりも予定通りに量をこなすことが大切なのだ。とくにジャカルタのオフィスに座っている責任者にとっては、これこそが最大の関心事である。お金を握っているのだから、仕事がきちんと行われなければ、支払いをストップすればよいのだが、それでは予定通りに仕事がこなせない。そうなると、責任者はまさに責任を問われる。
電話会議は1時間40分に及んだ。はじめのうち、この責任者は、復興住宅のレベルを上げればいいことは当然だが、具体的に何をすればよいのかと、居丈高であった。私は本人に会ったことはない。体も大きく、強引で扱いにくい人物だという。私たちの主張は、建築中の住宅の質をもっと真剣にモニターせよというところにある。そのためには、私たちが実施したようなファシリテータ相手のワークショップが有効であり、かれらに耐震性の大切さと、どうすれば健全な建物ができるかを理解してもらうことが大きな意味を持つ。
この電話会議で、私は、WSSIのチェアマンであり、国際地震工学会の会長であることを最大限に利用することにした。立場を利用したのは、ずるかったかもしれない。世界の地震工学関係者がこのプロジェクトの成り行きを見守るというのが、私の殺し文句である。MTFに出資した国々にとっても、お金が本当に有効に使われているかは大いに興味のあるところだと言った。「日本に帰ったら実情を訴えたい」とも言った。自分でも、多少ゆすりに近いという気がした。後で聞いたら、日本はMTFの出資国ではなく、住宅復興には参加していないということだった。知らないでよかったが、考えてみれば恥ずかしい発言だった。
最終的に、ジャカルタにいる世界銀行の責任者も、今後はもっと建物の質を確認して支払いを行うと言いはじめた。この発言に、ラジブはかなり満足していたようだが、本当に言ったとおりにやるかどうかは別問題だ。見守り続けるといっても限界がある。世界銀行のアカウンタビリティーが問われるのはこれからだ。
バンダアチェの海岸を見た
3日目の午後は、将来の家主、工事を行う人、その間を取り持つファシリテータが3点セットで待っている復興住宅の建設現場2ヶ所をまわった。
特に強い印象を受けたのは、最初に行った海岸に近い村である。二、三百メートルも行けば海岸線というほど海に近い。津波の前には砂浜かマングローブの植生であったところが、いまは、ねずみ色の土に覆われて跡形もない。津波で倒され流れついた巨木がそのまま横たわっている。延々と続く灰色の海岸にそって津波のあと土を盛り上げてつくった低めの堤防の間から、たくさんの家財道具が見え隠れしている。津波の前の生活がそのまま埋められているようだ。掘り返せば、犠牲者の遺体が出てきてもおかしくないように思えた。この海岸は死んでいる。いったいどれ位の時間がたてば、生き返ることができるのだろうか。
2ヶ所の復興住宅の村を訪ねて強く感じたことがある。家を建ててもらう人たちは、どうすれば地震に強い家ができるかなどほとんど知らない。それどころか、地震に強い家をつくらなければならないということ自体が十分わかっていない。津波の印象があまりに強かったため、インドネシアで次に起こるかもしれない災害は地震の揺れによる可能性のほうが高いとは考えていない。一方、請負業者(といっても、せいぜい3、4人のグループなのだが)の側には、もう何年もレンガを積み、鉄筋コンクリートの柱をつくり、大工さんとして仕事を続けてきたという自負がある。しかし、かれらもまた、地震に強い建物づくりの知識は無いにひとしい。
この間に立つファシリテータは、現場の経験が3年にも満たない人たちが9割を占めているのだ。これでは、ファシリテータに勝ち味は無い。外壁をきれいに仕上げてしまえば、鉄筋が十分入っているか、適切に配置されているかなどは、もはや判別できない。玄関をきれいにしてくれという家主さんの注文に応じてしまえば、見栄えはいいが耐震性が不足した住宅ができあがる。
さらに、私たちが見た現場では、住宅復興に伴うべき地域計画がまるでないところが多かった。道路も水道も、電気や下水も整備されないまま、住宅の建設だけが進められていた。しかも、必要とされる復興住宅の数さえ正しく見積もられなかったようで、出来上がった住宅が空き家のままのところも少なくない。
地震から2年が経ったバンダアチェは、ある種の熱気にあふれていた。世界中から救援の基金が流れ込み、それを使って工事を進める人たちが集まっている。NGOやNPOの名前を大きく車体に書いた自動車が走り回っている。車を馬に替えれば西部劇に出てくるブームタウンである。数年経って、救援資金という名のゴールドがなくなったら、この町はゴーストタウンにもなりかねない。世界中からの善意に基づく復興が、万一そのような惨めな形になってしまうとしたら、いったい人類の英知などというものはどこにあるのだろう。(全体の終わり)
Copyright (C) 2001-2012 Japan Association for Earthquake Engineering. All Rights Reserved.