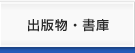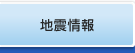書庫 > コラム
シドニーの頃−私の国際交流(その1)−
東京電機大学 教授 片山 恒雄
70歳になったばかりで思い出を書くのかという声があるかもしれない。だが、書いて悪いということもあるまい。覚えているうちに書いておきたいという気持ちもある。国際交流にかかわった私の経験をまとめてみたい。
東京オリンピックの年−シドニーに向かう
1963年の秋ごろだったろうか、オーストラリアのニューサウスウェールズ大学(シドニー)のショー先生が東京大学に来られた。航空工学科の林先生がイリノイ大学に客員教授として行っておられたときに一緒に過ごされた縁で、オーストラリアへ帰国の途中で日本に立ち寄られたのだ。私は、土木の修士2年だった。ショー先生は、構造工学のリラクセーション法という数値解析法で知られていた。土木工学科の何人かの仲間と一緒に航空工学科で開催された特別講義を聞きに行った。チョビ髭をたくわえた背の高い英国紳士といった風貌は、デビッド・ニーブンという英国俳優を思い出させた。講義の後、わからないことを聞きに行ったら、ていねいに教えてくださった。
しばらくして、ニューサウスウェールズ大学の土木工学科にティーチング・フェローという制度があるから、東大の学生で応募する人はいないかという手紙が、ショー先生から林先生に届いた。当時、外国に行くことは珍しかった。自費で行くにはお金がかかる。1ドル360円の時代である。それでも、米国に留学する人はいなくはなかったが、1960年代のオーストラリアは遠い遠い国だった。いまでも遠いことに変わりはないが、当時は、カンガルーと白豪主義とメンジース首相しか知らなかった。行きたいと手を挙げた学生がいなかったのである。
私は東大の修士課程の2年生だった。学部の4年間は、ラグビーの練習に明けくれ、授業にはあまり出なかったから、修士の2年間は新鮮で、博士課程にも進むつもりでいた。だが、指導教官だった伊藤学 先生(東大・名誉教授)に、「きみ、行ってみないか」と声をかけられたときには、迷わず、「はい」と答えていた。学部の4年間あまり授業に出なかったとはいえ、同じ大学に6年もいて、そろそろ違ったところに行ってみたいという気持ちがあった。
そんなことで、1964年3月の終わり、私は、シドニー空港に降り立っていた。東京オリンピックの年である。当時、航空機代は飛行時間1時間当たり約1万円といわれていて、20万円位しただろうか。母の長兄に借りた。直通便などというものはなく、香港、マニラ経由だった。空港には、ショー先生自身が、2人の大学院生と一緒に迎えに来てくださっていた。1960年代のことだ。日本から来る学生は、さぞかし頼りなく思っているだろうという配慮だったのではないか。
シドニーでの生活−勉強と遊びと
空港に迎えに来てくれた学生とは、博士課程をずっと一緒にすごした。そのうちの1人、マイケル・コリンズは、トロント大学教授として鉄筋コンクリートのせん断強度に関する研究者として知られる。日本にも何回か来て、鹿島建設と共同実験をしているし、JCIの大会(広島)で特別講演をしているので、ご存知の方もおられるだろう。この広島の会議には、私も神戸地震についての特別講演を頼まれていて、マイケル、奥さんのジュディーと私は、広島球場を見下ろす部屋で久しぶりの再会を楽しんだ。
マイケルとは、寮も一緒、そこを出て4人で借りた家での生活も一緒、彼の結婚式に出席したし、長男の洗礼にも立ち会った。長男が生まれるという夜、落ち着けないで、当時私が友人3人と借りていた家に来て、12時も過ぎてさぁ帰ろうと家を出たら、マイケルの車が盗まれていたというのも懐かしい思い出だ。車は数日後に出てきた。
ティーチング・フェローは、博士になるための研究をしながら、1週間に10時間ほど学生の実験や演習の指導をする。これに対して、学部卒業生の給料以上の奨学金がもらえた。中古の自動車を買うくらいの生活はできた。
博士論文のトピックを何にするかと聞かれたとき、私は、「高層ビルの振動をやらせてください」と答えた。オーストラリアにはほとんど地震がないから、地震のことを知っている人は少ないはずだ。(当時は、ブルース・ボルトというカリフォルニア工科大学の地震学の大教授がオーストラリア出身とは知らなかった。)それに比べて、こっちは、修士論文とはいえ、振動の問題をやったことがあったし、地震学や地震工学の授業だって受けていた。もともと言葉が不自由なのだから、せめて研究の中身では多少のハンデがほしい。きわめて不純かつ低次元な理由ではじめたことを、あれ以来ずっと続けることになった。
学生のときは、地震研究所の金井清先生に地震の「いろは」を教えていただいた、と言いたいところだが、正直なところ、先生の授業にはほとんど出席していない。そのかわり、シドニーでは金井先生の論文をたくさん読んだ。
シドニーの北の郊外にリバービュー修道院がある。昔から地震の観測所でもあり、ここに古い地震計があった。1923年9月1日、大森房吉先生が見ているときに針が大きく揺れだし、関東地震が起きたことを知ったという、嘘のような本当の話の、その地震計である。リバービュー修道院には、東大地震研究所の彙報が揃っていた。私は、ここに通って金井先生の論文を読んだり写したりした。修道院は丘の上にあって、イタリア製スクーター「ヴェスパ」で坂を上って行った。この中古スクーターはよく故障した。
シドニーでは、ずいぶん賭け事にお金を使った。シドニーで初めに住んだ学生寮と道を挟んで、シドニー最大の競馬場があった。この競馬場にはずいぶん通った。土曜日の日中には競馬、土曜日の夜はトロット、そして、日曜の夜にはドッグレースがあった。どれにも違った面白さがあった。その競馬場で、あるとき、ラグビー部の先輩に会った。こっちもびっくりしたが、相手もまさかあんなところで後輩に会うとは思わなかったろう。トロットは馬に引っ張られた2輪車レース、映画「ベンハー」を思い出してもらえばよい。先を走る車同士がぶつかったりすると、後続の車がそれに突っ込んで、とんでもない車が勝ったりする。ドッグレースでは、グレイハウンドが肉の臭いを付けたウサギの縫いぐるみを追って走る。一斉にコーナーにさしかかると、はじき飛ばされる犬もいるし、その前に「よーいどん」で箱のふたを開けても走らない犬もいる始末だ。そんな犬は、しばらく出場停止になる。
インターナショナル共同生活
3年の間に、4回住むところを変えた。最初の半年ほどは大学の寮、4人で一軒家を借りた「インターナショナル共同生活」を2回くり返し、最後の1年半ほどはロシア人の移民夫婦の家に賄いつきで部屋を借りた。
なんといっても思い出に残るのは、最初に寮を出たあとの4人の借家暮らしである。私のほかは,マイケル・コリンズ(ニュージーランド)、ニキータ・ボグダーノフ(ソ連)、カナガラトナム・ジェヤラサシンガムという長い名前のセイロン人であった。二キータは地理・地質学の著名な研究者になったが、ソ連が経済的にもっとも逼迫した時代に国の研究所の所長として苦労した。ジェリーは、スタンフォード大学の近くのソフトウェア・コンサルタンツにつとめている。
私の青春を代表するもののひとつは東大ラグビー部の4年間、そしてもうひとつがこの共同生活である。いろいろな思い出がありすぎる。
夕食は交替でつくった。車を持っていたのはマイケルだけだったから、朝はその車に乗せてもらって大学に通った。大学からそんなに遠かったわけでもなく、バスで行き帰りしてもそんなに時間はかからなかった。
土曜の午前中は全員そろって買いだし、午後は海岸。家はボンダイ・ビーチの近くだった。土曜か日曜の夜はみんなで映画に行った。こうやって書くと別に何のことはないようだが、充実した青春の日々だった。
第3回世界地震工学会議
シドニーに行った翌1965年の1月にニュージーランドで第3回世界地震工学会議が開かれた。私が外国の学会に参加したのは、このときが初めてだ。わが国の地震工学の研究者が大挙して外国での国際会議に出席した最初の機会でもあった。大挙といっても、せいぜい30人くらいだったと思うが、その人たちの多くにとっても、初めての外国出張だった。参加者の中では私がいちばん若く、次に若かったのが渡部丹さんだったと思う。
シドニーでの生活が10ヶ月ほどになり、英語にも自信がつきかけていた。日本の発表者への質疑に答えるお手伝いもやった。自信満々でもあったから、「きみは生意気だ」と怒った先生もおられたが、たしかにその通りだったのだろう。
会議の前半はオークランド、後半はウェリントンで開かれた。どちらでも、宿は2人部屋だった。オークランドでご一緒した先生は、町なかに「ノー・スタンディング」(停車禁止)とあるのを見て、「ここに立っていてはいけないんですか」と聞かれたし、毎晩ベッドカバーと毛布の間に入って寝ておられた。そんな時代だったのである。ウェリントンで同室になった先生は、最後の日に、「いろいろお世話になりました。何かの役に立ててください」と50ドルくださった。当時の私にとっては大金だったが、競馬に消えてしまった。
どの先生方も、もうみんなお亡くなりになった。周りにも、あのときのニュージーランドの第3回世界地震工学会議に参加された方は見当たらない。私は、初の国際会議ということで張り切っていた。毎朝、少し早めに起きて、その日に聞きたい発表の論文を読んでから会場へ行った。
オーストラリアの大学には、コロンボプランで留学しているアジア諸国からの学生がたくさん来ていた。この人たちが卒業したり学位を取って帰国した後で、オーストラリアに抱くだろう感謝の気持ちは、容易に想像できた。それに比べ、私が通っていたころの東大には、何人かの台湾からの留学生がいたに過ぎなかった。オーストラリアでの経験は、日本とアジア諸国の強い連携の大切さを私に教えることになった。
ところが、1967年に帰国してからしばらくの間、私は、この気持ちをすっかり忘れていた。(その1の終わり)
Copyright (C) 2001-2012 Japan Association for Earthquake Engineering. All Rights Reserved.