東北地方太平洋沖地震に関連した日本地震工学会の活動
2016年3月11日で、東北地方太平洋沖地震・東日本大震災の発生から5年となります。東北地方太平洋沖地震を受け、本会がまとめた提言、報告書、論文集等の情報発信、研究委員会活動等、主に本会の実施した活動についてまとめました。
東北地方太平洋沖地震 Website
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の発生後、本会東北地方太平洋沖地震対応委員会はClearinghouse Website「東北地方太平洋沖地震 Website」を立ち上げました。会員から提供された被害の情報、調査・研究に係わる情報等を収集し、ウェブサイトから情報発信しました。
「東北地方太平洋沖地震 Website」はこちら
提言
本会では、東日本大震災の翌年である2012年に「地震被害の軽減と復興に向けた提言」を作成しました。
提言の内容はこちら
合同調査報告
日本地震工学会、日本建築学会、土木学会、日本機械学会、地盤工学会、日本地震学会、日本原子力学会、日本都市計画学会の8学会合同で東日本大震災合同調査報告を刊行しています(全28編を予定・刊行中)。
本会会員は、他学会刊行分も会員特価で購入できます。詳細はこちらを参照して下さい。
強震データ
本会では、以下の機関より東北地方太平洋沖地震の強震データを提供いただき、頒布しています。
- 提供者:東京電力(株)
東京電力(株)福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所において観測された平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の本震記録(CD-ROM)<改訂版>
- 提供者:東北電力(株)
東北電力(株)女川原子力発電所における「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の余震等の加速度時刻歴波形データ」<追加>(CD-ROM)
- 提供者:日本原子力発電(株)
日本原子力発電(株)東海第二発電所における「平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震」の加速度時刻歴波形データ」(CD-ROM)
- 提供者:12電力会社
「南関東・福島県太平洋沿岸における岩盤の鉛直アレー観測網「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の本震・余震等の加速度時刻歴波形データ」
各強震データの詳細や入手方法はこちらをご参照ください(No.5~No.8が該当します)。
会誌
日本地震工学会誌では、下記の号で東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の特集をしております。
- 日本地震工学会誌 No.14 (Jul. 2011) [目次]
 [本文]
[本文] 
東日本大震災の発災にあたり/久保 哲夫
名誉会員に聞く/篠塚 正宣 東北地方太平洋沖地震:想像を超える被害
- 日本地震工学会誌 No.17 (Jul. 2012) [目次]
 [本文]
[本文] 
JAEE提言:地震被害の軽減と復興に向けた提言 −東日本大震災を受けて−/日本地震工学会
特集:次の巨大地震に備える
東日本大震災におけるトラフィック分析と接続性を考慮した
防災災害情報システム/内田 法彦、柴田 義孝
- 日本地震工学会誌 No.19 (Jun. 2013) [目次]
 [本文]
[本文] 
特集:防災力向上の取り組み
東日本大震災による静岡におけるソフト津波防災の見直し/阿部 郁男
シリーズ:TOHOKUナウ 復興に向けて(1)
石巻中心市街地の住民主導型復興まちづくり/姥浦 道生
- 日本地震工学会誌 No.20 (Oct. 2013) [目次]
 [本文]
[本文] 
特集:過去に学び、未来に備える (1)首都直下の大地震を考える
求められる都市・建築の総合的地震対策
〜東日本大震災における振動被害の実態と教訓を踏まえて〜/源栄 正人
シリーズ:TOHOKUナウ 復興に向けて(2)
防潮堤とまちづくり/平野 勝也
- 日本地震工学会誌 No.21 (Feb. 2014) [目次]
 [本文]
[本文] 
シリーズ:TOHOKUナウ 復興に向けて(3)
東日本大震災からの復興の特徴と課題/小野田泰明
- 日本地震工学会誌 No.22 (Jun. 2014) [目次]
 [本文]
[本文] 
シリーズ:TOHOKUナウ 復興に向けて(4)
名取市閖上地区の復興の現在/村尾 修
お知らせ:
東日本大震災合同調査報告「共通編1 地震・地震動」刊行のお知らせ
- 日本地震工学会誌 No.23 (Oct. 2014) [目次]
 [本文]
[本文] 
シリーズ:TOHOKUナウ 復興に向けて(5)
東日本大震災からの地域産業復興/増田 聡
学会ニュース:
「東日本大震災合同報告共通編3編」刊行記念シンポジウム
「地震災害再考、ファンダメンタルをふまえて」開催報告/本田 利器
- 日本地震工学会誌 No.24 (Feb. 2015) [目次]
 [本文]
[本文] 
シリーズ:TOHOKUナウ 復興に向けて(6)
石巻市の沿岸被災地の小学校における復興教育/佐藤 健
- 日本地震工学会誌 No.25 (Jun. 2015) [目次]
 [本文]
[本文] 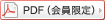
シリーズ:TOHOKUナウ 復興に向けて(7)
情報発信施設とまちづくり/小林 徹平
- 日本地震工学会誌 No.26 (Oct. 2015) [目次]
 [本文]
[本文] 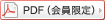
シリーズ:TOHOKUナウ 復興に向けて(8)
地域の住文化に根ざした木造による住まいの復興/岩田 司
- 日本地震工学会誌 No.27 (Mar. 2016) [目次]
 [本文]
[本文] 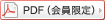
巻頭言:特集「東北地方太平洋沖地震5周年」について/高橋 郁夫
特集:東北地方太平洋沖地震5周年「震災復興と地震・津波対策技術(その1)
5年目の住宅復興 ─東日本大震災の仮設住宅・災害公営住宅・防災集団移転─/佃 悠
2011年津波による海浜変形・回復・復興/有働 恵子
東日本大震災からの産業復興と企業防災/丸谷 浩明
2011年東北地方太平洋沖地震の地震動/川辺 秀憲
東日本大震災の教訓を踏まえた地震ハザード研究/藤原 広行
非線形分散波理論による2011年東北地方太平洋沖地震津波の計算/馬場 俊孝
津波とピロティ構造/田中 礼治、澁谷 陽
JAEE Newsletter
JAEE Newsletterでは、下記の号で東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の特集ならびに関連記事の掲載をしております。
- 第1巻、第1号(創刊号)2012年9月 (Vol. 1, No. 1, September 2012)
NEWS WATCH -最新の研究・開発情報-
地球深部探査船「ちきゅう」を用いた「東北地方太平洋沖地震調査掘削」が終了
- 第2巻、第1号 2013年3月 (Vol. 2, No. 1, March 2013)
特集 東北地方太平洋沖地震から2年
NEWS WATCH -最新の研究・開発情報-
海溝軸付近における地震性滑りを実証「東北地方太平洋沖地震調査掘削」続報
- 第2巻、第2号 2013年6月 (Vol. 2, No. 2, June 2013)
特集 日本地震工学会論文賞受賞者から
- 第3巻、第1号 2014年3月 (Vol. 3, No. 1, March 2014)
特集 東日本大震災から3年
- 第3巻、第2号 2014年7月 (Vol. 3, No. 2, July 2014)
特集 各賞の受賞者から
EVENT REPORT
「東日本大震災合同報告 共通編3編」刊行記念シンポジウム
「地震災害再考,ファンダメンタルをふまえて」開催報告
- 第4巻、第1号 2015年4月 (Vol. 4, No. 1, April 2015)
特集 東日本大震災後の法・制度改正の動き
EVENT REPORT
東日本大震災合同調査報告「原子力編」刊行記念合同報告会 開催報告
- 第4巻、第2号 2015年8月 (Vol. 4, No. 2, August 2015)
特集 各賞の受賞者から
研究委員会
実際に即した設計津波波力の評価法や海域施設(養殖施設を含む)、陸域施設(橋梁、海岸林を含む)、建築物の具体的な津波対策とその指針を研究・提示することを目的として、2011年4月~2014年3月まで活動を行った。本委員会は2011年東北津波の発生前から計画されていたが、実際の活動は東北津波を強く意識したものとなった。
主な活動として、2011年東北津波の災害調査、災害調査成果の講演会(2011年:「東日本大震災の津波被害の教訓」)、日本地震工学会年会へのOSの提案(2012年:「津波災害とその対策・指針」、2013年:「海域施設、陸域施設、建築物の津波対策」)、研究成果の講演会(2014年:「津波荷重評価の最前線」)を行った。活動成果は報告書にとりまとめられている。
東日本大震災では、上下水道やガス、電力、通信などのライフラインに、広範な被害が生じた。本委員会は、福島県いわき市を対象に上下水道の地震被害のGIS(地理情報システム)データベースを構築した。さらに、いわき市水道局とは活動期間中に共同研究を締結し、被害や復旧に関するデータから学術研究を行った。得られた知見は市の上水道の更新計画の基礎資料として利用された。また、いわき市内の他のライフライン被害についても現地調査を含めて研究活動を行った。研究成果は、本会年次大会や日本水道協会研究発表会、第14回日本地震工学シンポジウムにおいて発表した。構築したGISデータベースについては、会員が利用申請の手続きをとれば利用できるよう、データベース協議会を設立した。ライフライン分野の研究だけでなく、幅広く、他の分野と融合した研究に活用し、被災地域の復興に還元していただきたい。アクセスは以下のURLを参照してください。 (http://ares.tu.chiba-u.jp/JAEELL/)
東日本大震災の影響を受けた原子力発電所の挙動、とりわけ東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓をふまえ、原子力発電所の地震・津波に対する安全を確保するための総合的な工学方法論を体系化するために、2012年9月~2015年3月の間、活動した。特に、「原子力システムにおける耐津波安全の基本要素」、「津波の作用・影響・工学的方法」、「社会との関わり」を包含する総合的体系の構築を目指し、そのために地震工学・津波工学・原子力安全工学にわたるシームレスな討議の場を形成した。活動成果は報告書にとりまとめられている(https://www.jaee.gr.jp/jp/2015/02/17/5894/)。また、密接に協力した日本原子力学会の学会誌(ATOMOΣ)2015年10月号~12月号に、活動成果を掲載するなど、多分野間の協働の実践に努めた。尚、委員会の3年半の活動は、以下のURLにも纏められている。(https://www.jaee.gr.jp/jp/research/archive/research06/)
- 委員長:後藤 洋三
- 設置期間:2012年8月1日~2016年3月31日
大津波や大都市直下地震等の突発災害から命を守るためには適切な避難対策が必要である。そのため、標記研究委員会を設け2012年8月から2016年3月の間、下記の4項目について調査研究活動を行った。
- (1)東日本大震災における津波避難の調査データ整理、分析、知見の発信
- (2)首都直下地震とそれが火災・洪水と複合化する場合の課題(2014年度より「首都圏における地震・水害等による複合災害への対応に関する委員会」に発展的に移行)
- (3)避難シミュレーション技術の利用環境の整備
- (4)海外における大規模避難の事例収集と情報交流
活動成果として、オーガナイズドセッションの開催(2012年と2013年の年次大会、2014年の第14回日本地震工学シンポジウム)、ワークショップの開催(2014年3月と2016年5月予定)、日本地震工学会論文集特集号「津波等の突発大災害からの避難の課題と対策」(2015年10月)の発刊、避難シミュレーションソフトVerificationとValidation (V&V)マニュアルとその適用事例の発刊、研究委員会報告書の発刊を行った。また震災対策技術展を活用してセミナーを6回開催した。
これらの内容は下記Webページで公開している。
https://www.jaee.gr.jp/jp/research/research05/
年次大会
日本地震工学会年次大会では、下記の大会で東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)を対象としたセッションを実施しております。梗概集を入手されたい方は学会出版物のページを参照してください。
- 日本地震工学会・大会-2011
オーガナイズドセッション・東北地方太平洋沖地震による橋梁被害
オーガナイズドセッション・東日本大震災における液状化被害の実態とその後の諸対応(その1)(その2)
オーガナイズドセッション・東北地方太平洋沖地震による強震動-地盤構造が地震動に及ぼす影響-(その1)(その2)
東日本大震災調査(その1)~(その4)
- 日本地震工学会・大会-2012
オーガナイズドセッション・東日本大震災における避難・対処行動
オーガナイズドセッション・東北地方太平洋沖地震および想定される巨大地震による強震動と地盤増幅特性の評価 その1、その2
オーガナイズドセッション・津波災害とその対策・指針
東日本大震災調査(その1)(その2)
- 日本地震工学会・大会-2013
オーガナイズドセッション・大災害時の避難問題(津波と洪水からの避難・対処行動および駅前滞留問題)
オーガナイズドセッション・海域施設、陸域施設(海岸林を含む)、建築物の津波対策
オーガナイズドセッション・津波災害とその対策・指針
東日本大震災調査、最近の地震被害調査
- 日本地震工学会・大会-2015
横断セッション・International Session:免震・制振
論文集
日本地震工学会論文集では、下記の号で東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)を対象とした特集号を公開しております。
International Symposium on Engineering Lessons Learned from the Giant Earthquake
東北地方太平洋沖地震から約1年後、2012年3月1日から4日にかけて、日本地震工学会、日本建築学会、土木学会、日本地盤工学会、日本機械学会および日本地震学会の共催で国際シンポジウム “One Year after the 2011 Great East Japan Earthquake – International Symposium on Engineering Lessons Learned from the Giant Earthquake –” を開催しました。このシンポジウムの論文集はこちらでご覧いただけます。
第14回日本地震工学シンポジウム
2014年 12月4日~6日にかけて、幹事学会の本会ほか計10学会の共催で第14回日本地震工学シンポジウム(14JEES)を開催しました。本シンポジウムでは、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)をテーマに多数の研究発表が行われております。発表プログラムはこちらでご覧いただけます。
第14回日本地震工学シンポジウム論文集(DVD版)の購入方法はこちらをご参照ください。
作成: 2016年3月 情報コミュニケーション委員会
2015年度 情報コミュニケーション委員会
委員長: 小檜山雅之(慶應義塾大学)
副委員長: 中村いずみ(防災科学技術研究所)
委員: 近藤伸也(宇都宮大学)、佐伯琢磨(防災科学技術研究所)、田川浩(広島大学)、多幾山法子(首都大学東京)、
畑山健(消防庁消防研究センター)、皆川佳祐(埼玉工業大学)、村上正浩(工学院大学)